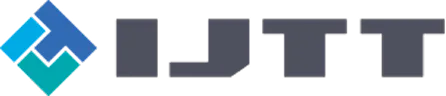ゼロからの挑戦が未来を創る
― 若手技術者から見たIJTTのこれから
2025.11.03
大きな変革期を迎えている自動車業界。その中で持続可能な企業として生き残っていくためには、技術の継承と進化、サステナビリティ、電動化など、あらゆる課題に取り組んでいく必要がある。
「これからのIJTT」に必要なものとは、いったい何なのか。 "若手技術者たち"が、今どんな思いで働き、これからどんなことを実現したい と考えているのか。
日々の仕事で感じていることや、挑戦したいテーマについて語ってもらった。

技術者としての道のり
現在入社8年目の商品企画部 商品企画グループのヨシダ、大学では機械系の学科で自動車について学んだ。その経験から、「勉強してきたことを実際の製品開発で活かしたい」と考え、IJTTに入社した。
現在は主にプロペラシャフトなど、シャフト系の設計を担当している。
そんなヨシダが今回担当したのは、EVトラック向けユニットとしてIJTTが提供するドライブシャフトの開発プロジェクト。電動化、自動化、コネクテッド化などの技術革新が同時に進行している中、IJTTも無関係ではいられない。社会のニーズにこたえられるように、EVトラック向けの製品開発にも着手することになった。
初めてのドライブシャフト開発で直面した未知の技術領域
「従来のドライブシャフトとの構造的な違いはそれほど大きくありませんが、EVトラック特有の要求仕様への対応が必要でした」と説明するヨシダ。しかし、ドライブシャフトの開発はIJTTにとって初めての取り組みであり、まったくの手探り状態からのスタートだった。
プロジェクトの第一歩は数々の製品や文献を調査し、試作検証では数えきれない失敗をした。
特に挑戦的だったのは、製品寿命の確保や発熱への対処法など、これまで経験したことのなかった技術課題に取り組んだこと。それは 設計技術者として大きく成長する機会となったという。

社会課題への貢献という付加価値
さまざまな工夫により、ついに実現したEVトラックのドライブシャフト。搭載された車両は、普通免許で運転できる3.5トン以下の小型トラックで、運転席から荷室へ直接移動できる設計となっている。取り回しがしやすく、物の積み降ろしや移動の負担が軽減され、ラストワンマイルの宅配効率向上に貢献している。
また、小型トラックは比較的軽量な荷物が中心となるため、ドライバーへの体力面の負担が少なく、女性ドライバーの活躍を後押しする要素にもなっている。人手不足が深刻化する物流現場において、こうした車両の導入は、より幅広い人材が物流の現場で活躍できるきっかけにもなる。
「同僚から、私たちが設計したドライブシャフトが搭載されたEVトラックが、実際に街中を走っている写真を送ってもらいました。自分たちが設計した部品が、実際に使われているのを見るのは、とてもうれしかったです」
女性活躍を支えるモビリティ開発に携われたことは、エンジニアとしても、また女性としても自らのキャリアの価値を実感できる大きなできごととなった。

ゼロからの開発への挑戦と技術領域の拡大
ヨシダは今後の展望について、カーボンニュートラルに貢献できるプロジェクトにも参加してみたいと話す。
「環境問題は私たちの世代が真剣に取り組まなければならない課題です。持続可能な社会の実現に貢献できる製品開発に携わりたい」。
また、技術者としてのさらなる成長も自身の目標として挙げた。「IJTTが扱っている製品はモビリティの駆動系・パワートレイン、エンジンやその周辺部品もあれば、産業用ロボット部品など多岐にわたります。商品開発として、これまでの技術にとらわれない分野にも挑戦してみたいですね」。
将来的には、技術者として幅広い視野を持ち、工程全体を通した製品開発に関わっていくことが自分の目指す姿だと、迷いのない表情で語る。

技術継承への責任と持続可能な企業への想い
IJTTの魅力についてヨシダは「さまざまな製品開発に挑戦している点」を挙げる。技術革新が加速する現代では、製品の市場寿命は短命化しており、長期的な安定性よりも、持続的かつ先進的なアップデートが求められる。IJTTは、そうした変化に対応するだけでなく、カーボンニュートラル社会の実現に向けて藻場の再生に関する実証実験にも参画するなど、モビリティ分野にとどまらない挑戦を続けている。「特定分野に留まらず、幅広い技術領域で新しいことに挑戦できる環境があることが、技術者として大きな魅力ですね」。
さらに「先輩たちは本当にいろいろな分野の知識を持っていて、いつも的確なアドバイスをくれます。私もそんな技術者になりたいです」とほほ笑む。先輩から学びつつ、自身も後輩のためにマニュアルを作成するなど、技術継承に積極的だ。
「先輩方が築いてきた技術を次の世代に伝えていくことが、私たちの責任だと思います」
若手ながら技術継承への責任感を持ち、新たな挑戦を求めるヨシダのような社員が、持続可能な企業を支える大切なピースとなっている。